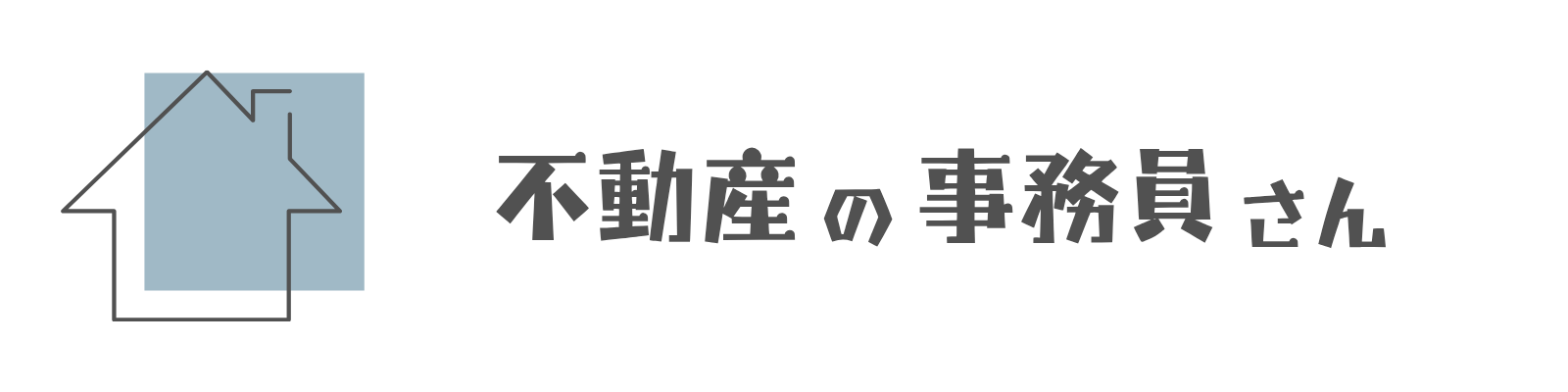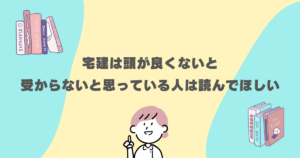宅地建物取引士試験に臨む際、合格のチャンスを高める有力な制度がある「5問免除制度」をご存知ですか?
この制度は簡単に言うと、一定の条件を満たした受験者に対して、試験の最後の5問を免除してもらえるものです。
本ブログでは、この5問免除制度の概要や適用条件、免除される問題の範囲と傾向について詳しく解説します。
また私は、5問免除を利用せずに受験、5問免除者として受験の両方経験があるので、メリットなども合わせてお伝えしていきます。
宅建5問免除制度とは?

宅建5問免除制度は、宅地建物取引士試験において特定の条件を満たす受験者に対する有利な措置です。
この制度を利用することで、受験者は46~50問目の5問を免除され、合格する可能性を少し高めてくれます。
免除の対象者
この制度は、主に宅建業に関わる業務をしている受験者が対象です。
宅建業に関わる業務をしていると言っても、単に不動産会社に所属しているだけでは業務とはいえず、細かいルールが設けられています。
- 従業員名簿に記載がある
- 従業者証明書を所持している
- 2日間にわたる講習を受けテストに合格する
従業員名簿に記載されている人は【主として宅建業務を日常的に行っている人】という扱いなので、この名簿に記載されていれば業務の条件クリアです。
従業員名簿に記載がある人はおそらく従業者証明書(免許証のようなもの)も発行してもらっているはずなので、こちらも期限切れなどがないか確認しておきましょう。
講習については後ほど説明します。
ただし、名簿に記載されていても実際には実務はしていないというグレーな人は、不正受講にならないよう、免除対象になるかどうか事前に会社や専門学校などに聞いてみましょう。
上記で分かる通り、基本的に一般受験者はこの免除を受けることができません。
5問免除の適用条件と申請方法

冒頭でも述べましたが、宅地建物取引士(宅建士)試験において5問免除制度を利用するには、いくつかの必須要件を満たすことが必要です。
申請には特定のステップを踏む必要があります。本章では、免除制度を適用するための要件と申請手続きの具体的な流れについて詳述します。
免除制度の利用条件詳細
5問免除が適用されるためには、以下の二つの条件を満たす必要があります。
宅建業従業者証明書の取得
– 宅建業に携わっていることを証明するために、勤務先から「宅建業従業者証明書」を受け取ることが必須です。この証明書は正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も取得可能であり、実務経験の長さに関わらず申請に利用できます。
登録講習の修了
– 国土交通大臣の登録を受けた教育機関が実施する登録講習を受講し、修了試験に合格することが条件です。この講習は宅建業に従事していることを前提としており、一般の参加者は受講することができません。修了試験を通過することで、登録講習修了者として認められます。
申請・講習受講の流れ
登録講習への申し込み
登録講習の登録講習機関一覧
– 最初に、登録講習を実施している教育機関に申し込む必要があります。これらの機関は、国土交通大臣から認可を受けている必要があり、受講料やカリキュラム内容を比較し、自分に合った機関を選ぶことが重要です。通信講座での学習
– 申し込みが完了すると、教材が自宅に発送され、約1〜2ヶ月の期間中に自主学習します。この時点で課題の提出はないため、自分のペースで学ぶことができますが、試験範囲をしっかりと学習しておくことが求められます。スクーリングへの参加
– 登録講習の一環として、対面での講義が行われます。この講義は通常1〜2日間で、約10時間程度です。また、一部の機関ではオンライン形式の講義も提供されています。修了試験の実施
– スクーリング後には修了試験が行われ、講習で学んだ内容が出題されます。合格基準は、20問中70%以上の正解となるため、十分な準備が必要です。登録講習修了者証明書の取得
– 修了試験に合格した場合、登録講習修了者証明書が発行されます。この証明書は発行日から3年間有効であり、宅建試験を受ける際に利用できます。宅建試験の申し込み
– 宅建試験の申し込みは毎年7月頃から行われます。その際、修了者証明書を添付し、5問免除制度を利用する旨を申請します。申し込みは、郵送またはウェブで行うことができ、各自のスタイルに応じた手続きを行うことが可能です。
以上のように、5問免除制度を利用するためには特定の条件と手順を満たす必要がありますが、この制度は合格のチャンスを広げる重要な機会でもありますので、対象者の方はぜひ利用してみてください。
5問免除対象者ではない人ができる試験対策

対象ではなかった人は、しっかり自力で5点満点取れるよう対策していきましょう。
落としても1点、最悪2点までにおさえておきたい科目です。
免除対象となる問題の内容
5問免除の対象となる問題は、次のようなテーマが含まれます
- 土地に関する性質や地目、種類
- 建築物の形状、構造及び種別
- 宅地や建物の需給に関連する法規及び実務の知識
- 毎年の不動産に関わる統計より出題
これらの問題は、日常的な知識や最新の市場データを基に出題されることが多く、受験者にとっても理解しやすい内容が特徴です。
出題傾向について
過去の試験を分析すると、5問免除の問題は比較的予測がしやすく、実生活や業務での実務に密接に関連するトピックが多いことが分かります。具体的には、専門的な知識だけでなく、一般的な常識に基づいて解答できる問題が多いことが特徴です。
常識に基づく問題
免除対象となる問題は、法律の知識よりも、一般的知識が重要視されることが多いです。土地や建物の取引に関する基本的な理解や地形に関する知識が問われるため、実務的な観点からの理解が役立つ場面が多いです。
最近の統計情報の反映
近年では、統計データに基づく問題がほぼ毎年1問出題され、受験者には最新の情報や市場動向についての把握が求められています。パーセンテージの数字の暗記物や、上がったか下がったかどっち?みたいな問題が出たりします。
5問免除の効果的な学習法
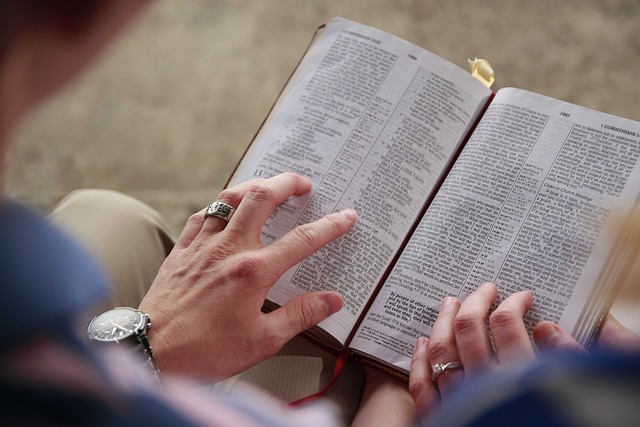
過去問を重視する
5問免除科目の出題傾向を把握する上で、過去問学習は非常に重要です。過去数年分の問題を繰り返し解くことで、どのような問題が出題されやすいかを見極めることができます。問題の形式や内容に慣れることで、試験当日も落ち着いて解答できるでしょう。特に、頻出項目に関しては重点的に対策を取ることで、得点の確保が見込めます。
ただし統計問題に関しては、最新の数字の傾向を元に出題されるので、過去問をやってもほとんど意味がありません。
直前期9月頃から【今年の統計データ】ここが狙われます!みたいな講義をいろんな学校や講師が発信しだすので、その情報を待ちましょう。
常識を活用する
5問免除科目には、常識で解ける問題も多く含まれています。日常生活や社会常識に基づいた判断が求められるため、特に景表法や土地・建物に関する問題では、直感を信じることも大切です。
ただし、場合によっては知識が必要となることもあるため、経済や法律の基礎知識を並行して学習しておくと、本試験に対する安心感が増します。
暗記技術の活用
5問免除科目では、知識を効率よく暗記する技術も活用できる要素です。フラッシュカードを作成したり、マインドマップを利用して視覚的に整理することで、記憶の定着を図ることができます。特に重要な用語や定義は繰り返し思い出して確認しましょう。
集中した直前学習
試験直前の一週間またはそれに近い時期に集中して学習することが推奨されます。
長期間にわたって漠然と勉強するのではなく、直前期に内容を詰め込み、記憶に定着させることが効率的です。この期間中は、特に重要なポイントや過去問を中心に学習を進めると良いでしょう。
直前期、この5問に沼ることだけは避けましょう。他の項目に自信がない場合はそちらを優先するのが最適です。
5問免除を利用するかを判断するためのメリット・デメリット

5問免除制度は、多くの受験者にとって魅力的な選択肢ですが、利用するかどうかを決定する際には慎重にメリットとデメリットを考える必要があります。以下に、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
メリット
学習時間の有効活用
免除される問題は地形や建物、不動産の基礎知識に関連した内容が中心です。
地形は昔理科で習ったような内容が出たことが多いです。建物に関しては建築の知識のほうがメインなので、常識では解けないような問題がでてくることもありました。
考えれば分かる問題と、完全暗記問題、少し勉強が必要な問題が5問入っている感じです。
私が一番大きなメリットに感じたのは、この5問が免除されると、その分の時間を他の重要な科目、例えば「宅建業法」や「権利関係」などに集中して学習することが可能になったことです。
たったの5問とはいえ、この5問に対しての勉強時間や記憶量が積み重なると、他の科目の勉強時間が圧迫され、かなり損している感じでした。
免除される問題に関しては、別途学習する必要がなくなります。これにより、より難易度の高い法律やその他の科目に時間を割くことができます。そのため、全体的な勉強の効率が向上します。
デメリット
費用の負担
登録講習を受講する際には、数万円の費用がかかります。具体的には、登録講習の受講料は15,000円から19,000円程度が相場です。会社から取得を求められている場合は、補助してくれたりするところもあるようなので、確認してみましょう。
時間と手間
登録講習には、通信講座とスクーリングの受講が必要です。スクーリングの日程調整は、不動産の休日に合わせて、火曜日や水曜日を主とした平日に行われることが多いため、仕事と両立する場合は有給を取得しなければならないことがあります。
どんな理由でも、当日講習や修了試験を欠席してしまうと再調整ができず、5問免除対象者として認められないため、注意しましょう。
他にも考慮すべきポイント
制限時間の減少リスク
5問免除を受ける場合、試験時間が10分短縮されます。このため、時間の使い方に対して常に注意が必要です。
特に初めて免除対象者になった人は、いつもより早めのペースで解答を進める必要があります。
事前に模試などで時間配分を計測して対策しておきましょう。
宅建5問免除についてのまとめ
5問免除制度は合格率向上に有効な手段ですが、制度利用には一定のコストと手間がかかることも事実です。
自身の状況とトレードオフを検討し、この制度がプラスの効果をもたらすかどうかを慎重に見極め、うまく利用しましょう。